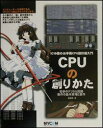移転前のサイトからの転記です。日付は当時のものを使用しています。文言などは若干修正を入れています(7年前なので表現が若くて恥ずかしい……一部修正済み)。
TD4関連記事は4bit-CPU TD4で管理しています。
秋葉原の電気街で部品を集めてきました。秋月電子・千石電商・マルツで大体揃いますね。前回の記事で紹介した汎用ロジック等と合わせて、全部品収集完了です。
今回購入したものは以下です。

代替品
予算とリードタイムの関係で以下2点の部品は代替品を購入しました。
・ダイオードネットワーク D9-1C
(設計時採用品) D9-1C
(代替品) DN9-1C
前回の記事でD9-1Cはチップワンストップで最安¥204/個とお伝えしましたが、某電気屋さんで¥100/個を発見……!!ROMのマトリックス部で使う逆流防止用ダイオードなので16個必要。単純に¥1,600も節約できる!!と考えていたところ、型番がDN9-1Cであることに気付きました。
販売代理店HPを見てみたところ、どうやら正式な代替品のようです。こちらのデータシートを確認しても、品質に影響のある違いは無さそうです。

・ユニバーサル基板 ICB-98GU
(設計時採用品) ICB-98GU
(代替品) ICB-96GU×2
ICB-98GU、¥4,350とか高すぎる!!笑 その隣に98GUを2当分した96GUなるものが¥970でこちらを見ていたのでこれを2枚購入しました。重ねて使えるようにピンヘッダーも購入しましたが、並べるほうが楽かなーと使い方は悩み中です。8bit DIPスイッチが安価なものだとダサいものしかなかったので、ROM部分を下段にして隠せたらいいですね。またついでに格好いい赤い基板も購入しておきました。テキストの表現を借りれば3倍性能がいいはず。

その他部品
・ブザー
ブザーには自励式のTMB-05なるものを購入。自励式は素子内に発振回路があるので、他励式のように駆動信号を別回路で作って入れる必要が無くて楽なようです。定格電圧5V、平均消費電流(Max)30mAととても使いやすい。少し高いですがいい買い物をしました。

・コンデンサ
クロック生成用の無極性電解コンと普通の電解コン。普通の電解コンには音響用を選んでみました。笑 音響用は一般的なコンデンサよりもヒステリシスの歪みが改善されていたり、インピーダンスが小さかったりするらしいです。ただ一番の決め手は色が格好良かったからです。

・リード線
電源用にAWG24の赤、GND用にAWG24の黒、そして信号線用にAWG28の紺を購入しました。信号線はもう少し細い(AWG値が大きい)ものが良かったかなーとも思いましたが、散々悩んでAWG28を購入しました。