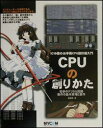移転前のサイトからの転記です。日付は当時のものを使用しています。文言などは若干修正を入れています(7年前なので表現が若くて恥ずかしい……一部修正済み)。
TD4関連記事は4bit-CPU TD4で管理しています。
TD4はなかなかに大規模で複雑な配線となるので部品配置と仮想配線は大事です。実装時間の短縮とバグ削減のためと言ってますが、経験のためやってみましょうという意味合いが強いかなと思います。
今回使用するソフトは開発支援ソフトでも紹介しているユニバーサル基板エディタ「PasS」です。まずは部品情報を作成する必要があるのですが、これがとにかく大変で心が折れること請け合いです。デフォルトで入っている部品は数が少ないんですよね。
今回作成が必要な部品は以下の4点。
・ユニバーサル基板 ICB-96GU 表裏
・DN9-1C
・セラコン 2.54mmピッチ
・セラコン 汎用ロジックICピッチ
特にGU型番のユニバーサル基板はもともといくつかのパターンが引いてあるので、それを描いていたら日が暮れても終わらないよなあと思っていたところ、こちらのブログに98GUの部品データが置いてあるじゃないですか。この改造だったら96GUも何とかなるかな……と考えながら制作者様に感謝して頂戴致しました。それにしても先程のブログ、ロジックICで自作の8ビットCPUなんて完全にTD4の上位互換じゃないですか。笑
そうこうしているうちにICB-96GU表裏とDN9-1Cの部品データ作成を終えました。セラコン2.54mmピッチのデータはヘッドホンアンプ・プラスアルファ #4 基板で仕上げ(完成編)から頂きました。基板は半田面を作成してから、左右反転させて灰色のパターンを基板色で埋めて完成。DN9-1Cはピンソケットのデータを元に9ピン長方形部品にして完成。以下に画像ファイルとして置いておきます。
◯ICB-96GU
◯DN9-1C
◯セラコン 汎用ロジックICピッチ
PasSのマニュアルを読むと、基板の幅は最上部の黒色(R, G, B)=(0, 0, 0)の場所で判断しており、部品のピン位置は赤色のドットで判断しているようです。

一時はどうなることかと思いましたが、次回から部品配置と仮想配線がスタートできそうです。